近年、アプリが病気の治療のための医療機器として注目されています。アプリを用いた治療は「デジタルセラピューティクス」や「デジタル治療」などと呼ばれ、症状が改善しにくかったり、治療が難しかったりする病気への新たなアプローチだといえるでしょう。
開発も盛んに行われており、中にはすでに病院やクリニックで導入されているものも。
本記事では、治療用アプリの特徴やメリット・デメリットなどを解説。販売中のアプリや、今後の販売が待たれるアプリについてもご紹介します。
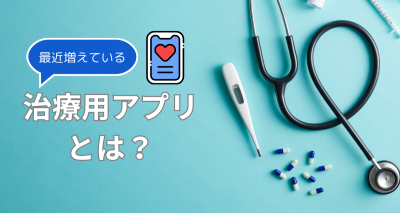
ADHD、ニコチン依存もアプリで改善!? 近年開発が相次ぐ治療用アプリとは
治療用アプリの特徴
健康管理に用いられるアプリには、ダイエットアプリや食事管理アプリなどがありますが、治療用アプリとそれらは異なるのでしょうか。また、治療用アプリにデメリットはないのでしょうか。
ここでは、治療用アプリの特徴について、解説します。
治療用アプリは自由に使えるの?
治療用アプリとは、病気の治療や症状の改善を目的としたデジタルツールを指します。一般的にイメージされる治療として薬剤や手術などがありますが、新たに加わった選択肢といえるでしょう。
治療用アプリは薬剤同様、基本的に医師の診断を受けたうえで処方され、利用に際して医師や医療機関から発行されるコードの入力が求められます。そのため、アプリストアなどでのダウンロード自体は可能な製品もあるものの、一般的なスマートフォンアプリと違って、自由に使用できません。
また、ほかの治療法と併用するものが多く、アプリ単独で治療を完結できるわけではないことに留意が必要です。
ヘルスケアアプリとの違いは?
治療用アプリと似たものとして、ダイエットアプリや運動アプリなどのヘルスケアアプリをイメージする方もいるでしょう。しかし、これらと治療用アプリは異なります。
以下に、ヘルスケアアプリと治療用アプリの違いをまとめました。
| ヘルスケアアプリ | 治療用アプリ |
|---|---|
|
・健康管理・生活習慣の改善が目的 ・自由にダウンロード・利用が可能 ・無料または低コスト |
・疾患の治療や症状の改善が目的 ・利用には医師の処方が必要 ・有料 (基本的にヘルスケアアプリよりも高額) |
ヘルスケアアプリは主に日常的な健康管理や生活習慣改善を目的としており、多くの場合、アプリストアで自由にダウンロードして利用できます。
禁煙サポートや睡眠障害の対策など、似た目的を持つ治療用アプリもあるものの、ヘルスケアアプリは「医療行為または保健指導などを行うものでない」「疾患等の治療、症状の改善、その他の健康改善効果または生活改善効果を保証するものではない」などの記載が利用規約にあることからわかるよう、厚生労働省による承認が必要な治療用アプリとは別の基準のもとに作られた製品です。
使用に際しては医師の診断や治療に代わるものでもないことに留意しましょう。
ヘルスケアアプリで健康管理を始めたい方はこちら
治療用アプリの開発が盛んな理由は?課題はある?
心拍数や睡眠時などをモニタリングできるスマートフォンアプリが増えたり、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の影響でオンライン診療が普及した結果、医療者・患者ともに医療でアプリやスマートフォンを用いることへの抵抗が緩和されたりしたことなど、治療用アプリの開発が盛んな背景として、近年の社会的な変化が挙げられます。
そのほか、治療用アプリが持つメリットもアプリ開発を後押ししています。一方で、治療用アプリには課題があるのも事実です。具体的な内容を見てみましょう。
治療用アプリのメリット
治療用アプリのメリットとして、以下の2点が挙げられます。
治療の精度や継続率が上昇する
治療用アプリは患者のデータを継続的に蓄積できるため、医師が患者一人ひとりに合った治療・サポートを行いやすくなります。一方、患者側は日常的に自分の状態をチェックすることで、行動変容が促されます。
そのため、生活習慣病など、自己管理やセルフケアが重要な病気では、治療を継続できる可能性が高まるでしょう。ゲーム要素を取り入れるなど、継続しやすい工夫がなされたアプリも登場しつつあります。
さらに、オンラインで情報を共有できるので、来院が困難な精神疾患などでも経過観察が可能な点も挙げられます。
このように、従来は治療やその継続が困難だった患者でも、対応できる点がメリットです。
医療費の抑制につながる
治療の効果が高まったり、治療が継続できたりすると、早期回復や重症化予防につながります。
その結果、医療費の抑制というメリットが期待でき、社会的意義からも開発が進められています。
治療用アプリの課題
治療用アプリの課題として、患者にITリテラシーが求められる点が指摘されています。高齢者や子供では、家族のサポートが必要なこともあるでしょう。
医療機器として扱われるため費用がかかるうえ、日本で保険適用となっているアプリが少ない点も課題といえます。
現在販売されている治療用アプリ
| 対象疾患 | 商品名 | 状況 | 製造販売 |
|---|---|---|---|
| ニコチン依存症 | CureApp SC ニコチン依存症 治療アプリ 及びCO チェッカー |
2020年12月 保険適用 |
CureApp |
| 高血圧症 | CureApp HT 高血圧治療 補助アプリ |
2022年9月 保険適用 |
CureApp |
※2025年3月7日時点
2025年3月時点で、2つの治療用アプリが日本で保険適用となっています。それぞれどのようなアプリか、ご紹介します。
ニコチン依存症治療アプリ『CureApp SC』
引用元:PR TIMES
『CureApp SC』は、治療用アプリとして2020年12月に日本で初めて保険適用された製品で、ニコチン依存症患者が対象です。
治療プログラム機能や禁煙日記機能、チャット機能などが搭載されており、患者自身が禁煙行動を継続できるようサポートしてくれます。また、専用機器「COチェッカー」で呼気中の一酸化炭素濃度を測定し、その結果をアプリに無線通信で記録します。
アプリは、禁煙治療薬と併用が条件で、薬剤の費用も含めた治療の自己負担額は3ヵ月で約28,000円です*1。
*1 禁煙治療における保険適用についてより。健康保険を使用して3割負担の場合の金額
高血圧治療補助アプリ『CureApp HT』
『CureApp HT』は、高血圧患者を対象とした治療アプリです。
生活習慣改善のための目標の設定や取り組みをアプリが支援してくれるので、それらを通じて血圧低下を目指します。また、血圧や活動の記録をアプリに入力すると、医師がそのデータを確認し、治療をサポートしてくれます。
アプリを用いた治療の自己負担額は、月々2,370円です(診療に応じた料金が別途必要。初月は150円が追加で必要)*2。
*2 CureApp HT 高血圧治療補助アプリ 血圧チャレンジプログラムより。健康保険を利用して3割負担の場合の金額
ADHD、アルコール依存症も。今後販売が待たれる治療用アプリ
▲日本でADHD治療にアプリが利用される日も近い(画像は海外で販売されているADHD治療アプリ『EndeavorRx®』)
引用元:Google Play
すでに製品段階にある治療用アプリも複数あります。2025年3月現在、以下のアプリの販売準備が進行中です。
| 対象疾患 | 商品名 | 状況 | 開発 | 販売 |
|---|---|---|---|---|
| アルコール 依存症 |
CureApp AUD 飲酒量低減 治療補助アプリ |
2025年2月 製造販売承認取得 |
CureApp | サワイグループ ホールディングス |
| ADHD (小児期) |
ENDEAVORRIDE (エンデバーライド)® |
2025年2月 製造販売承認取得 |
Akili, Inc. | 塩野義製薬 |
| 不眠障害 | Med CBT-i | 2023年3月 製造販売承認取得 |
サスメド | サスメド |
※2025年3月7日時点
アルコール依存症を対象とした『CureApp AUD』はすでに製造販売承認を取得しており、2025年中の保険適用と販売を目指すことが、販売元のサワイグループホールディングスから発表されています。
小児期のADHDに対する治療アプリは、海外では『EndeavorRx®』としてすでに使用されています。日本では『ENDEAVORRIDE(エンデバーライド)®』として販売予定で、製造販売承認は取得済み。
販売元の塩野義製薬に問い合わせたところ、2025年度中の発売を目指しているとのことです。
また、不眠障害に対する治療アプリ『Med CBT-i』も製造販売承認を取得しています。開発元のサスメドは保険適用希望書を取り下げましたが、引き続き事業化の検討を継続する旨を発表しています。
このほか、慢性心不全、慢性腰痛症、2型糖尿病、うつ病など、さまざまな病気に対する治療アプリの開発が進んでいます。
製薬会社など参入企業も増えており、治療アプリがスタンダードとなる日も近いでしょう。
(文 ばんしょうふみえ)
こちらの記事もおすすめ
