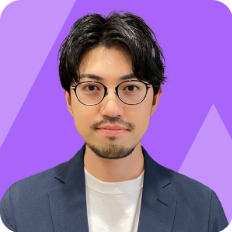2025年7月23日、アプリの計測・分析ツールを提供するAdjust主催のアプリマーケティングカンファレンス「Adjust Ignite Tokyo 2025」が開催されました。
業界のトップマーケターが集結し、最新トレンドやグロースのノウハウが惜しみなく共有された本イベント。会場は終始活気に満ち、多くの注目を集めました。
後編では、カスタマージャーニー設計の実践例から広告効果の再定義、さらには世界に挑むスタートアップの成長戦略まで、アプリビジネスの最前線が語られたセッションの模様をレポートします。

【イベントレポート】業界注目マーケターが集結! Adjust ignite Tokyo 2025(後編)
レポート前編はこちら
最適なカスタマージャーニーの設計について
カスタマージャーニーとは、ユーザーが商品やサービスを認知し、関心を持ち、購入・利用・継続・離脱に至るまでの一連の体験や行動を「旅」に見立てて可視化するマーケティング概念です。各フェーズにおける接点や課題、感情の変化を整理することで、より適切な接客や導線設計を行うための思考ツールとされています。
AIによる自動最適化が進む現在、あらためて人がジャーニーに向き合う意味を問い直す本セッションでは、ユーザー理解に基づいた設計、現場でのモニタリング、柔軟な改善プロセスといった実践知が共有されました。
登壇したのは、ゲーム・美容医療・メディアと、異なる業界で活躍する3社。それぞれが描く“最適なカスタマージャーニー”には、業種の枠を超えて応用可能な示唆が詰まっていました。
プレイヤー心理に寄り添う設計と“現場感覚”を活かした分析で継続を支える
『キングダム 頂天』や『ブルーロック Project: World Champion』など、人気IPを活用したゲームアプリを展開するルーデル株式会社の吉永氏は、「ゲームアプリにおけるカスタマージャーニーの設計は、まず、新規ユーザーと既存ユーザーで戦略が異なる」と語りました。
新規ユーザーに対しては、認知から登録、初回プレイ体験を通じて「このゲーム、面白そう」という価値を感じてもらい、日常的にログインして遊ぶ“定着”までのステップを丁寧に設計しているとのことです。一方で、既存ユーザーには、継続利用を促す動機付けや、離脱ユーザーの復帰を支える導線設計を行い、ユーザーにあわせた施策を実行していると説明しました。
中でも特徴的だったのは、「ユーザー同士の交流」を価値指標として重視している点です。特にチャットの使用頻度は、ユーザーがそのゲームに“居場所”を感じているかどうかの定量的な指標になりうると述べました。
ログイン頻度やチャット数、コミュニティ内の行動などを多角的にモニタリングし、全体設計と連動させることで、より深いインサイトを得ることが可能になるといいます。さらに、新規・既存に分けるだけでなく、インストール時期や課金額など、さまざまな区分でカスタマージャーニーを設計しているそうです。
▲ルーデルのカスタマージャーニーマップ
吉永氏は「データ分析にはドメイン知識、つまりユーザー目線が不可欠」と強調。数値だけを見てもプレイヤーの心理までは読み取れないため、現場で培った感覚や仮説と向き合いながら、柔軟に検証を繰り返す姿勢が重要だと述べました。
経験や勘を否定するのではなく、そこに数値的根拠を重ねていくことで、“最強のデータドリブン”が完成すると語り、プレイヤー心理に深く寄り添い、戦略的に設計された分析こそが継続を支えるカギになるとまとめました。
ユーザー心理に寄り添う設計と、一次情報を起点にした共感マーケティング
国内最大級の美容医療・整形の口コミ予約アプリ『トリビュー』を運営する株式会社トリビューの冨岡氏は、美容医療という繊細な意思決定が求められる領域において、「“(カスタマージャーニーの)どのフェーズが重要か”ではなく、各フェーズにおいてカスタマーが抱える不安や課題、ニーズを丁寧に把握することが大切」だと紹介しました。
同社では、ユーザーの行動を「施術検討フェーズ」「情報収集フェーズ」「予約・施術先決定フェーズ」「施術後の感想共有フェーズ」という4つのステップに分けて、カスタマージャーニーを設計しているそうです。
例えば「情報収集フェーズ」では、「顔を小さくしたい」「目元をはっきりさせたい」といった漠然としたお悩みを、具体的な施術名へとつなげていくプロセスをサポート。ダウンタイムの長さ、施術後の経過画像、口コミなどの情報をUI上で統合することで、ユーザーが抱える不安や疑問を自然に解消できる体験設計を重視していると語りました。
とくに印象的だったのは、ユーザーインタビューを積極的に活用している点です。マーケター自身が1時間単位でユーザーと直接対話し、「なぜ施術を検討したのか」「施術体験後にどう感じたのか」といった感情の変化を丁寧にヒアリングしているとのことです。こうして得られた一次情報は、広告コピーやクリエイティブ設計に反映され、共感と成果を両立するマーケティングに活用されています。
さらに冨岡氏は、「美容医療には200以上の施術があり、全体最適を図るのは現実的ではない」と指摘。その上で、施術ごとにターゲットやインサイトを丁寧に分析し、個別最適な施策を積み重ねていくことが有効だと強調しました。ユーザーの悩みとニーズに寄り添いながら、“個別最適を積み重ねる”ことこそが、確実な成果につながる重要な要素であると語りました。
ジャンル横断型メディアに求められる文脈理解と構造的ジャーニー設計
24時間編成のチャンネルを軸に、ニュース、恋愛リアリティショー、スポーツ、アニメなど多ジャンルを展開する動画配信サービス『ABEMA』。中澤氏は、「サービスの性質上、コンテンツのジャンルごとにユーザー属性や接点が異なり、単一のカスタマージャーニーで語ることはできない」と語りました。
例えば恋愛リアリティショーを好む層と、麻雀番組を視聴する層では、認知経路から視聴習慣、利用継続の動機までがまったく異なります。中澤氏は、こうした多様な文脈に対応するためには、「ユーザーの置かれた状況や動機を丁寧に理解し、それぞれに最適化された体験を構造的に設計することが重要」だと強調しました。
設計フェーズでは、「Who(誰に)」「What(何を)」「How(どう届けるか)」のフレームを軸に、定量・定性の両面からターゲットの解像度を高め、どのようなメッセージが響き、どのような便益が行動を促すかを言語化。SNSや広告といったチャネルも最適に選定し、ユーザーに届く形に落とし込んでいるとのことです。
さらに中澤氏は、「設計なき執行は意味がない」と述べ、設計・執行・モニタリングの3軸をセットで実行することの重要性を説きました。『ABEMA』では、スプリント型の施策運用に加えて、PDCAを日次で回す体制を構築。異常値が出た際には当日中にアクションを起こすなど、スピード感を持った施策執行を徹底しているといいます。
モニタリング体制についても、トラッキング可能な領域と不可能な領域に分けて設計。トラッキング可能な内部では、データクリーンルームやサーバー連携によって精度を担保し、トラッキング不可能な領域ではMMM(マーケティング・ミックス・モデリング)を用いて、広告施策の間接的な効果も定量的に捉えているとのことでした。
こうした全方位型の取り組みにより、『ABEMA』ではジャンルごとの文脈を捉えたジャーニー設計と実行が、継続的な視聴とユーザーとの関係構築につながっているようです。
個別最適の積み重ねが、“本質的な体験設計”につながる
本セッションでは、ゲーム、美容医療、メディアと異なる業種でユーザーと向き合う3名が登壇し、それぞれのカスタマージャーニー設計の実践を紹介しました。
領域やKPIが異なる中で共通していたのは、ユーザーの感情や行動に寄り添い、柔軟に設計・改善を重ねる姿勢です。印象的だったのは、いずれの企業も「ユーザーごとの文脈」を丁寧に読み解いていたことでした。
カスタマージャーニーとは、あらかじめ定められた道筋をなぞるものではなく、ユーザーの状況や動機に応じて仮説を立て、現場感覚とデータを掛け合わせながら設計と検証を繰り返していく営みなのだという考え方が、随所ににじんでいました。
その広告、本当に効果がありますか?
広告施策は、本当にユーザー獲得に貢献しているのか――。その問いに向き合うための指標として注目されているのが、「インクリメンタリティ(Incrementality)」です。
インクリメンタリティとは「増分効果」のことで、アプリマーケティングにおいては、広告を配信したことによって“実際にどれだけの成果が上乗せされたのか”を測定する考え方です。単なるCV(コンバージョン)数やCPA(顧客獲得単価)では判断できない、「広告がなかったら生まれなかった成果」を明らかにする手法として注目が高まっています。
(参考:https://www.adjust.com/ja/glossary/incrementality/)
本セッションには、エンタメ、住宅、不動産、美容・健康といった異なる業界でユーザー獲得を担う3名が登壇。広告効果の「見かけの成果」と「実質的な成果」をどう見極めるか、そして施策全体をどのように最適化していくのかについて、実践から得た知見に基づく議論が展開されました。
“増分効果”で見極める広告の真価、インクリメンタリティで再定義するCV評価
映画・ドラマ・アニメ・バラエティなど、幅広いジャンルのコンテンツを提供する動画配信サービス『Hulu』を展開するHJホールディングス株式会社の戎氏は、「広告の効果を語るうえで、すべてのCVを一律に扱うべきではない」と語ります。
数字の裏にある“ユーザーの行動や背景”に目を向けることで、広告の本質的な貢献が見えてくるといいます。
▲6パターンのCV事例(Hulu)
同社のマーケティング部門ではこれまで、広告経由のCVのみを指標としていたため、オーガニック流入の効果は組織内で正確に評価されていませんでした。しかし現在は、全体のCVを統合的に捉え、広告の貢献度を割り戻して社内で再評価する運用へと移行しています。
セッション内では、MMM(マーケティング・ミックス・モデリング)を用いた効果分析や、ツールを使わずに検証した事例が紹介されました。例えば、ある広告枠では「実広告」と「ダミー広告」を用いたA/Bテストを実施。テストグループには通常の広告を、コントロールグループには広告主と無関係なダミー広告を配信し、双方のCV数を比較しました。
その結果、ダミー広告でもCVが発生するケースが見られ、「広告がなくても獲得できていた枠」が可視化されました。こうした差分からインクリメンタリティ(広告による“増分効果”)を把握し、枠ごとの配信調整に活かしているといいます。
また、検索広告の必要性はタイミングによっても変化します。たとえば地上波ドラマの最終回後に「続きは『Huluオリジナルストーリーで』」と告知するケースでは、ユーザーが自発的に検索・流入するため、広告がなくても自然にCVが伸びる傾向があります。一方で、長期休暇や話題映画の公開タイミングなど“VODサービスの需要”が高まる局面では、広告による流入の取りこぼし防止が重要になります。
戎氏は最後に、インクリメンタリティの検証結果をもとに、アプリとWebを横断したクロスデバイスでのユーザー行動を捉え直し、効果の高い接点に重点的に予算を投下する運用へとシフトしていると語り、今後も、ルートやプラットフォームにとらわれず、ユーザー起点で最適なマーケティングを追求していく姿勢を示しました。
ブレンデッドCPAを軸に、全体最適を見据えたプロセス設計へ
不動産物件情報検索プラットフォームサービス『ニフティ不動産』を運営するニフティライフスタイルの増尾氏は、「ペイド広告の成果だけを追い求めると、本来オーガニックで獲得できたはずのユーザーにまでコストをかけてしまう事態に陥りがちです」と語ります。
実際、同社が新たに出稿した媒体では、広告経由のダウンロード数は増加したものの、同時にオーガニック流入が同等の割合で減少し、全体のDL数は横ばいという結果になりました。
この事象を受け、同社では広告効果の評価指標を媒体別のCPAから、ペイドとオーガニックを合算した「ブレンデッドCPA」へと変更。出稿効果を一面的に捉えるのではなく、全体での成果として評価する方針へと転換しました。
▲実際に発生した事象(ニフティ不動産)※スライド内の具体数字はダミーデータ
▲課題に対する理想像(ニフティ不動産) ※スライド内の具体数字はダミーデータ
評価指標に合わせてチーム体制も再編。従来はペイドとオーガニックを別チームで運用していましたが、両チャネルを横断的に評価するため連携を強化しました。KPIも個別から「全体CV」へと再定義し、組織全体での評価軸の統一を図っています。
分析面では、ローデータでのユーザー行動分析を実施。その結果、従来のリターゲティング広告は配信とCVがユーザーの離脱直後に集中しており、「広告がなくても自然にCVした可能性のあるユーザー」にまでコストをかけているという仮説が浮かびました。
そこでこの仮説に基づき「離脱直後のユーザー」を配信対象から除外。当該媒体のROASは低下したものの、これまで広告で獲得していたユーザーがオーガニック経由のCVとなり、全体のCV数は増加。広告費をより本質的な投資に振り分け、ブレンデッドCPAの観点で全体最適につながったといいます。
「広告の評価は、単一の効率指標では測れません。ユーザー行動を多角的に捉え、全体の成果として見る視点が必要です」と語る増尾氏。チャネルごとの数字にとらわれず、ユーザー視点で設計された広告運用が、成果の本質を捉えるカギであると強調しました。
LTVと態度変容、そして“間接効果”まで――広告の“本当の効き方”を見極める
AI食事管理アプリ『あすけん』を展開する株式会社askenの渡辺氏は、「広告が本当に“効いた”かどうかは、CV(コンバージョン)だけでは判断できない」と語ります。
CPAやクリック率といった短期指標にとどまらず、LTV(ライフタイムバリュー)やユーザーの態度変容、広告によって生まれる“間接的なオーガニック流入”も含め、広告効果を立体的に捉えているとのことです。
例えば、広告経由で獲得したユーザーの継続率や課金率を追い、LTVを可視化。これにより「CPAは安いが継続しない」チャネルと、「獲得数は少なくても長期的に価値を生む」施策を見極めています。
また、広告接触後すぐにCVに至らなくとも、記憶に残ったことで後日検索を経て自然流入につながるケースもあり、「広告がオーガニック流入を押し上げている可能性も見逃せない」と渡辺氏は述べます。
実際に、若年層向けに出稿したショート動画広告の直後、オーガニックでの新規入会が想定を超えて増加。行動パターンや属性の一致などから、広告接触後の自然流入である可能性が高いと判断しました。媒体の数値とも相関が見られ、間接効果としての手応えを得たといいます。
▲スライド:ショート動画広告の事例(あすけん) ※スライド内の具体数字はダミーデータ
「すべての施策で検証できているわけではない」と前置きしつつも、今後はツール導入も視野に入れながら、検証環境の整備を進めていく考えを示しました。最後に渡辺氏は、「単にCPAを下げることを目指すのではなく、ユーザーとの“より良い出会い”を設計していきたい」と語りました。
指標を“再定義”することで見えてくる、インクリメンタリティ起点の広告運用
本セッションでは、『Hulu』『ニフティ不動産』『あすけん』といった異業種のマーケティング担当者が登壇し、広告効果を「本当に効いたのか」という視点から捉え直す姿勢が共有されました。
共通して見られたのは、「広告の成果はクリック率やCPAだけでは測りきれない」という問題意識と、より本質的な価値を見極めようとする取り組みです。
中でも印象的だったのが、“インクリメンタリティ(増分効果)”という視点でした。CVが発生したという事実の裏側に、「そのCVは広告によるものだったのか? 広告がなければどうだったのか?」といった問いを立て、ユーザーの行動や背景を丁寧に分析しようとする姿勢が随所に見られました。
広告は、ユーザーとの接点のひとつに過ぎません。重要なのは、その後にどのような行動や体験が生まれたのか。定量指標の裏にある“文脈”や“変化”を読み解くことで、広告の価値を再定義していこうとする各社の姿勢が、今回のセッションを通じて浮かび上がっていました。
【特別対談】世界に挑むスタートアップから学ぶアプリグロース戦略
App Store無料ランキング1位を獲得したテキスト通話アプリ『Jiffcy』、そして訪日外国人向けの商品説明アプリとして、インバウンド需要の回復とともに存在感を高める『Payke』。いずれも、ユニークな発想と圧倒的なユーザー体験を武器に、国内外のアプリ市場で注目を集めるスタートアップです。
本セッションでは、「Forbes 30 Under 30 Asia 2019」に選出されたPaykeの古田氏と、日経トレンディ「スタートアップ大賞」受賞、および「2025年ヒット予測ベスト100」で第10位にランクインしたJiffcyの西村氏が登壇しました。
ジャンルは異なりますが、アプリというプラットフォームを活かして世界を目指す両者が、ストア1位の裏側、グロースに必要な視点、そして“これから挑みたい未来”について語り合いました。
1位獲得の裏にある「出会う体験」の最適化
訪日外国人向けの商品説明アプリ『Payke』を運営する株式会社Paykeの古田氏は、ユーザーが商品に出会う“入り口の体験”をいかに最適化するかに注力してきたと語ります。
バーコードをスキャンするだけで、商品の情報を母国語で得られるという仕組みは、言語の壁を感じる訪日観光客にとって、買い物を“あきらめないための手段”として高い支持を得てきました。
アプリは、オーガニックな拡散を起点に成長しました。初期には、Facebookへの投稿動画がバズったことをきっかけにランキング1位を獲得。その後も、ユーザーやマイクロインフルエンサーによる自然な投稿が拡散を後押ししたといいます。
注目すべきは、投稿の“見せ方”を分析し、画面の映えやシーンの切り取り方を意識して設計していた点です。「KOC(Key Opinion Consumer)の投稿がバズると、フォロワーの多いインフルエンサーが追随する」という心理的メカニズムを踏まえ、バズを設計していたと説明しました。
マーケティング施策では、「Paykeを紹介する動画」を作るのではなく、「日本に行くならDLしておきたいアプリ◯選」といった文脈をつくることで、広告色を抑えた拡散にも成功しました。さらに、流行らせたい国の母国語で音声をつけるなど、文化ごとの“入り口”にも細かく対応しているといいます。
海外展開においては、「多言語対応のUI設計」や「国ごとの表現の違い」にも徹底的にこだわっています。例えば、同じ“10%OFF”の表示でも、台湾では“90%”と表現されるなど、数字の捉え方すら異なるそうです。こうした細部まで現地に合わせ、「現地アプリだと錯覚するほどの自然なUX」を追求していると語りました。
今後は、日本人が海外でも使えるようなグローバル展開に加えて、蓄積されたデータをもとに越境EC領域などへの展開も構想しているとのことです。古田氏が描く、“言語の壁を超えるインフラ”としての進化に期待が高まります。
Jiffcy 西村:文化を超える“親しみ”が、ストア1位のカギに
テキスト通話アプリ『Jiffcy』を開発・提供する株式会社穴熊の西村氏は、「誰でも直感的に“遊べる”体験」にこだわってきたと語ります。Jiffcyは、電話をかけてテキストで応答するというユニークな形式の通話アプリです。声を出さずに“話す”という体験は、音声通話でもチャットでもない、新しいコミュニケーションの形を提示しています。
App Store総合1位を獲得できた背景として、西村氏は「初回体験の良さ」を挙げました。機能を詰め込むのではなく、初めて触れた人が“なんとなく楽しい”と感じられるよう、UIや導線を極限まで削ぎ落としたといいます。通話画面やインタラクションはあえて説明不要なデザインに徹し、実際の対面会話に近い“間”や“雰囲気”を再現することで、心の距離を縮める工夫をしているとのことです。
注目すべきは、Jiffcyの成長が広告や大型インフルエンサーに依存していない点です。テレビ番組での紹介やスタートアップ大賞の受賞をきっかけとした露出もありましたが、最も効果があったのは、その後の記事がYahoo!ニュースに転載されたタイミングだったと振り返ります。
西村氏は「影響力のあるメディアへの掲載を逆算して狙う動きが重要」と語り、メディア戦略についてもプロダクトと同様に“自然な共感”を軸に設計していることがうかがえました。
グローバル展開においても、「文化が違っても“親しみ”が伝わるかどうか」を最重要視しているそうです。現地ユーザーに実際に使ってもらい、どこで迷うのか、どこが気持ちいいのかを見極めながら、UI/UXを調整。表現やユーモアの捉え方など、国ごとの微妙な違いにも丁寧に対応している姿勢が印象的でした。
今後について、西村氏は「テキスト通話を作りたいのではなく、誤解なく伝わる“テレパシーのようなコミュニケーション”を追求したい」と語ります。Jiffcyはその一歩にすぎず、まだつながれていない人と人が“ゆるくつながる”世界をつくるための挑戦は、これからが本番だと意欲を見せました。
スタートアップのグロースに共通する“体験解像度”へのこだわり
2社の話に共通していたのは、「届けたい体験を徹底的に突き詰める姿勢」でした。ストアランキングで1位を獲得することは目的ではなく、ユーザーの生活や心理に寄り添った機能設計、そしてその“体験価値”をいかに伝えるかという工夫の積み重ねが、結果として評価されたにすぎません。
また、グローバル展開において印象的だったのは、単なる英語対応では通用しないという現実です。文化や行動様式の違いを前提に、現地のユーザーが「自分のためのアプリ」だと自然に感じられるようなUX設計が求められます。
スタートアップが成長を遂げるカギは、正解のない市場環境の中で、プロダクトの核となる体験を深く理解し、愚直に磨き続けることにあります。その姿勢こそが、世界と向き合うスタートアップに共通する“グロース戦略の本質”であるといえるのではないでしょうか。
アプリグロースの伴走者が語るアプリマーケティング最前線
スマートフォンアプリ市場の成熟にともない、新規ユーザーの獲得が難しくなるなかで、継続率やLTV(ライフタイムバリュー)の最大化がますます重視されるようになっています。そんな現在、プロダクトに寄り添いながらグロース支援を行う“伴走者”たちは、何を考え、どのようなアクションを実行しているのでしょうか。
本セッションには、パブリッシャーおよびアプリのメディアパートナー事業を展開する株式会社フォーエムの佐藤 立 氏、マーケティングツール「Repro」を提供するRepro株式会社の中野 竜太郎 氏、そしてショート動画広告領域で急成長を遂げている株式会社Yaahaの秋山 裕武 氏が登壇しました。
それぞれ異なる立場からアプリマーケティングを支える3名が、現場で直面する課題や、これからの時代に求められる戦略について語りました。
収益性とユーザビリティを両立する、広告活用のリアルな戦略とは
アプリの収益化における広告活用の最前線について語ったのは、フォーエムの佐藤立氏。AnyMind Groupでは、アーティストのマネジメントやプロテインブランドの展開など、幅広い事業を展開しており、アプリ領域では200以上の支援実績と100本超の自社運営実績を誇ります。佐藤氏が重視するのは、自社運営で得たデータに基づく広告マネタイズ戦略です。
「代理店の枠にとどまらず、自分たちで試すことに意味がある」と語り、その具体例として紹介されたのが、アーティストとコラボした自社アプリです。イベントと連動させることで、広告費をかけずにローンチ初日でストア1位を獲得。熱量の高いファンを起点にバイラルが生まれ、限られた予算でも成果を上げることができたといいます。
また、ユーザーがどのようにアプリをインストールしているかという傾向についても注目されています。近年、Google Playでは「指名検索」が主流となっており、偶発的な発見は減少傾向にあります。佐藤氏は、「アプリは“見つけてもらう”時代から、“指名される”存在になる必要がある」と指摘しました。
さらに、国内では課金中心のビジネスモデルが主流である一方、海外では広告収益の比率が高い国も多く、展開先によってマネタイズ設計を柔軟に変えていくことが求められます。
「国内だけで戦うのではなく、海外で勝てる市場を見出す視点が重要」と述べ、広告とユーザー体験の最適なバランスを追求する姿勢こそ、今のアプリマーケターに求められる視点であると語りました。
“使い続けられるアプリ”を設計するために、今マーケターが持つべき視点
アプリマーケティングオートメーションツール「Repro」を提供する中野竜太郎氏は、600人以上が所属するアプリマーケター向けコミュニティを主宰し、ユーザー行動や市場の変化をデータと実践の両面から捉えています。
中野氏がまず指摘したのは、アプリ利用スタイルの変化です。「現在は短時間・スキマ時間に頻繁に使えるアプリが伸びています」と述べ、継続利用を前提とした“習慣化されるプロダクト設計”の重要性を強調しました。多くのアプリでは、インストール初日に約9割のユーザーが離脱するという現実がある中で、「使い続けてもらう仕組み」をいかに作るかが、今後の鍵になると語ります。
その上で、「CPIやCPAといった表面的な指標だけでなく、LTVから逆算して投資判断を行う視点が重要」と提言しました。プロダクトの本質に立ち返った設計が、長期的な成果につながるといいます。
また、中野氏は自身のトレンドキャッチアップ方法についても共有しました。日々20ヵ国以上のアプリストアを分析し、VPNと生成AIを活用して「日本ではまだ知られていない注目アプリ」を抽出しているとのこと。「世界で流行したアプリは、1年半〜2年後に日本でもトレンドになる傾向があります。今だけでなく、先を読む力を養ってほしい」とアドバイスを送りました。
さらに、「アプリ外決済」への備えも見逃せないと述べ、「制度が変わる今、アプリ外での設計を怠れば大きな差が生まれる」と警鐘を鳴らし、ユーザー体験を軸にしたマーケティング設計の再考を呼びかけました。
ショート動画がアプリの成長を後押しする――パフォーマンスを生むクリエイティブとは
ショート動画広告の波が再びアプリマーケティングに熱をもたらしている――そう語るのは、ショート動画広告に特化したプロモーション支援を行う株式会社Yaahaの秋山裕武氏です。過去4年間にわたる支援実績をもとに、「一度落ち着いたTikTok広告への注目が、再び高まってきている」と現場の変化を伝えました。
その背景には、アルゴリズムの進化や配信の学習最適化があり、広告のパフォーマンスも改善傾向にあるといいます。秋山氏がとくに強調したのは、「再現性ある成果を生むクリエイティブ」の重要性です。
検索広告のように運用の調整で差が出る領域とは異なり、ショート動画広告では「最初の1秒でユーザーの手を止められるかどうか」がすべて。クリエイティブの摩耗スピードも早いため、「同じ動画を使い続けるのではなく、フォーマットや訴求を常に変えて検証を繰り返すことが不可欠」と語りました。
こうした前提のもと、Yaahaでは70人以上のクリエイティブディレクター&クリエイターと運用担当が密に連携し、完全内製体制で高速なPDCAを実現。訴求軸や構成パターンを繰り返し検証しながら、成果を再現できる「型」を磨き上げているとのことです。
さらに、有名インフルエンサーに頼らなくても、「構成や見せ方次第でCPA・CPIは改善できる」と秋山氏は語ります。LTVが長くなりやすいアプリだからこそ、クリエイティブを主軸としたショート動画広告には大きな可能性があると述べました。
「アプリをプロモーションする価値は、今なお十分にある」。変化の早い広告環境の中でも成果を出し続ける組織と思想こそが、アプリグロースを支えているのです。
これからのアプリ戦略に生かす、3人のキーマンの実践的アプローチ
本セッションでは、アプリグロースを支援する3名が、現場で積み上げてきた知見に基づいた具体的なアクションを共有しました。
フォーエムの佐藤氏は、自社運営で得たデータを起点にした広告戦略を提示。Reproの中野氏は、使い続けたくなる設計や海外トレンドの先読みを通じて、LTVを見据えたマーケティングの重要性を説きました。Yaahaの秋山氏は、成果を再現するためのショート動画クリエイティブ運用の実態を紹介しました。
アプリグロースの本質を見極め、今の市場で本当に効果のある施策を模索するマーケターにとって、多くのヒントが詰まったセッションとなりました。